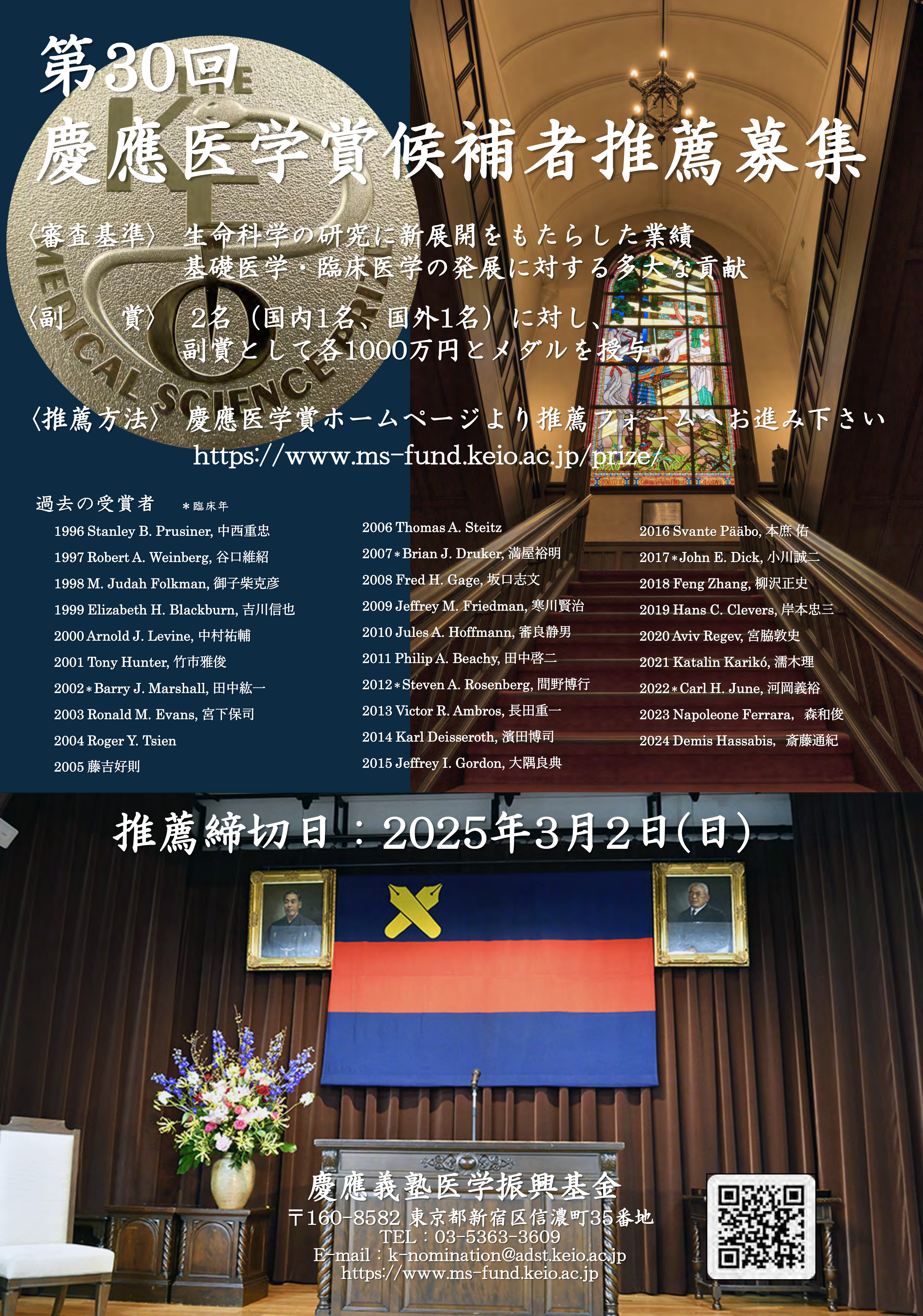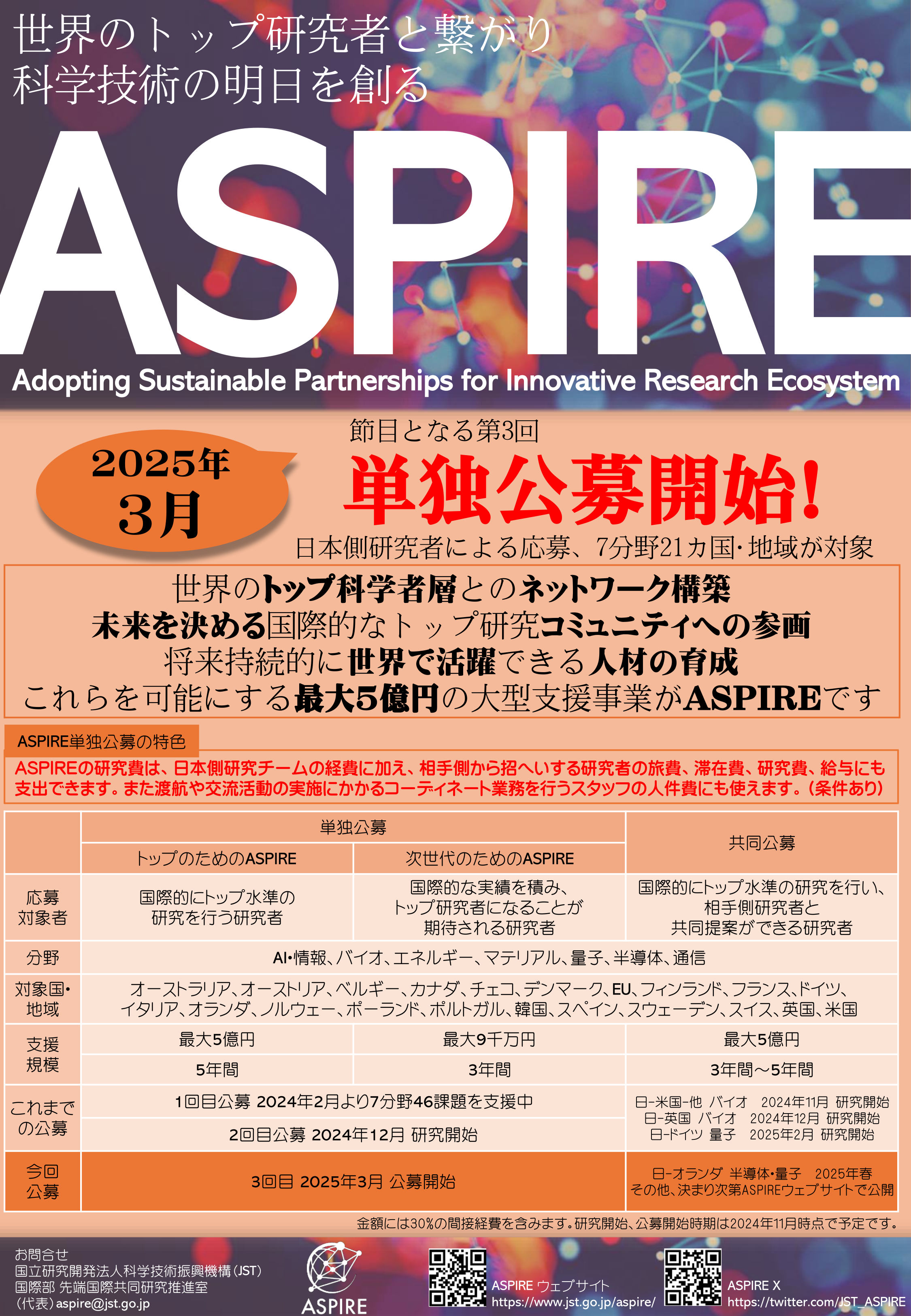2025.02.28
第2回日本発生生物学会フロンティア賞 公募要領
趣旨:日本発生生物学会は独創性の高い研究で今後の発生生物学をリードする若手研究者を表彰します。
表彰の名称:JSDB Frontiers Prize(正式名称は英文)、日本発生生物学会フロンティア賞(国内向け)
表彰対象者:日本発生生物学会員
※第77回日本細胞生物学会・第58回日本発生生物学会合同大会若手賞への申込は、妨げない。
応募方法:表彰されることを希望する会員本人が以下の書類(英語または日本語)を作成し、jsdbadmin@jsdb.jpまでメールで提出ください。
JSDB Frontiers Prize表彰候補者略歴書 (WORD28KB・PDF109KB)
・独創的な研究に至った背景と経緯、研究のセールスポイント、今後の研究展望を自由形式で記述してください。
・略歴、これまでの研究経歴、業績、を様式に沿って記入ください。
・必須ではありませんが、サポートレター(同僚、共同研究者、スーパーバイザ等からの応募者の独創性を示すシンボリックな話も歓迎)を提出ください。
*なお未発表データについては審査に際してconfidentialに扱います。
審査方法:提出書類に基づいて審査委員会で書面審査により候補者を絞った上でオンラインでの面接審査を行います。
審査委員はGender、年齢、所属機関などの多様性を広く確保し、理事を含む11名の会員が担当します。第2回審査委員は以下の会員が担当します。
熱田勇士(九州大、第1回受賞)、入江直樹(総研大)、川口茜(遺伝研、第1回受賞)、日下部りえ(関西大学)、見學美根子(京都大)、中村輝(熊本大)、林利憲(広島大・副幹事長)、平島剛志(MBI, 第1回受賞)、藤森俊彦(基生研・教育担当理事)、三井優輔(京大、第1回受賞)、和田洋(筑波大)
オブザーバー:高橋淑子(京都大・会長)
なお、受賞者には次回の審査委員を担当していただきます。審査委員は1年ごとに半分入れ替えます。次回の審査委員は、第2回審査委員会から提案し理事会において決定されます。メンター、利害関係者はその審査に加わりません。
審査基準:一個人に対し、表彰は1回に限ります。毎年最大で3名程度を表彰します。
受賞講演:受賞講演として大会期間中の指定されたセッションにおいて英語で発表してもらいます。受賞者は必ず受賞講演のセッションに参加、講演ください。なお、大会期間中の一般演題での発表もできますので、積極的に一般演題の登録もお願いします。
本賞:賞状
副賞と招待Gift and invitation:受賞者は、日本発生生物学会が他国の発生生物学関連団体と開催する発生生物学合同大会を含む海外で開催される国際学会等に参加・発表する旅費のサポート(サポート期限は受賞決定から3年以内、上限は30万円)を受けられます。
さらに、受賞者は日本発生生物学会が発行する国際誌であるDevelopment, Growth & Differentiationにこれまでの研究や今後の発生生物学の新展開について記事の執筆をDGD編集幹事より招待されます。
第2回JSDB Frontiers Prizeの公募スケジュールは以下の通りです。
募集期間:2025年3月1日から15日
(第77回日本細胞生物学会・第58回日本発生生物学会合同大会の演題登録期間とは違いますのでご注意ください)
書類審査期間:2025年3月16日から30日 (面接候補者への通知は4月15日まで)
面接審査期間:2025年5月1日から30日の間 (オンライン面接後、理事会で決定)
受賞者決定・公開:2025年7月1日
受賞講演:2025年7月17日(木)11:55-12:55
表彰の名称:JSDB Frontiers Prize(正式名称は英文)、日本発生生物学会フロンティア賞(国内向け)
表彰対象者:日本発生生物学会員
※第77回日本細胞生物学会・第58回日本発生生物学会合同大会若手賞への申込は、妨げない。
応募方法:表彰されることを希望する会員本人が以下の書類(英語または日本語)を作成し、jsdbadmin@jsdb.jpまでメールで提出ください。
JSDB Frontiers Prize表彰候補者略歴書 (WORD28KB・PDF109KB)
・独創的な研究に至った背景と経緯、研究のセールスポイント、今後の研究展望を自由形式で記述してください。
・略歴、これまでの研究経歴、業績、を様式に沿って記入ください。
・必須ではありませんが、サポートレター(同僚、共同研究者、スーパーバイザ等からの応募者の独創性を示すシンボリックな話も歓迎)を提出ください。
*なお未発表データについては審査に際してconfidentialに扱います。
審査方法:提出書類に基づいて審査委員会で書面審査により候補者を絞った上でオンラインでの面接審査を行います。
審査委員はGender、年齢、所属機関などの多様性を広く確保し、理事を含む11名の会員が担当します。第2回審査委員は以下の会員が担当します。
熱田勇士(九州大、第1回受賞)、入江直樹(総研大)、川口茜(遺伝研、第1回受賞)、日下部りえ(関西大学)、見學美根子(京都大)、中村輝(熊本大)、林利憲(広島大・副幹事長)、平島剛志(MBI, 第1回受賞)、藤森俊彦(基生研・教育担当理事)、三井優輔(京大、第1回受賞)、和田洋(筑波大)
オブザーバー:高橋淑子(京都大・会長)
なお、受賞者には次回の審査委員を担当していただきます。審査委員は1年ごとに半分入れ替えます。次回の審査委員は、第2回審査委員会から提案し理事会において決定されます。メンター、利害関係者はその審査に加わりません。
審査基準:一個人に対し、表彰は1回に限ります。毎年最大で3名程度を表彰します。
受賞講演:受賞講演として大会期間中の指定されたセッションにおいて英語で発表してもらいます。受賞者は必ず受賞講演のセッションに参加、講演ください。なお、大会期間中の一般演題での発表もできますので、積極的に一般演題の登録もお願いします。
本賞:賞状
副賞と招待Gift and invitation:受賞者は、日本発生生物学会が他国の発生生物学関連団体と開催する発生生物学合同大会を含む海外で開催される国際学会等に参加・発表する旅費のサポート(サポート期限は受賞決定から3年以内、上限は30万円)を受けられます。
さらに、受賞者は日本発生生物学会が発行する国際誌であるDevelopment, Growth & Differentiationにこれまでの研究や今後の発生生物学の新展開について記事の執筆をDGD編集幹事より招待されます。
第2回JSDB Frontiers Prizeの公募スケジュールは以下の通りです。
募集期間:2025年3月1日から15日
(第77回日本細胞生物学会・第58回日本発生生物学会合同大会の演題登録期間とは違いますのでご注意ください)
書類審査期間:2025年3月16日から30日 (面接候補者への通知は4月15日まで)
面接審査期間:2025年5月1日から30日の間 (オンライン面接後、理事会で決定)
受賞者決定・公開:2025年7月1日
受賞講演:2025年7月17日(木)11:55-12:55