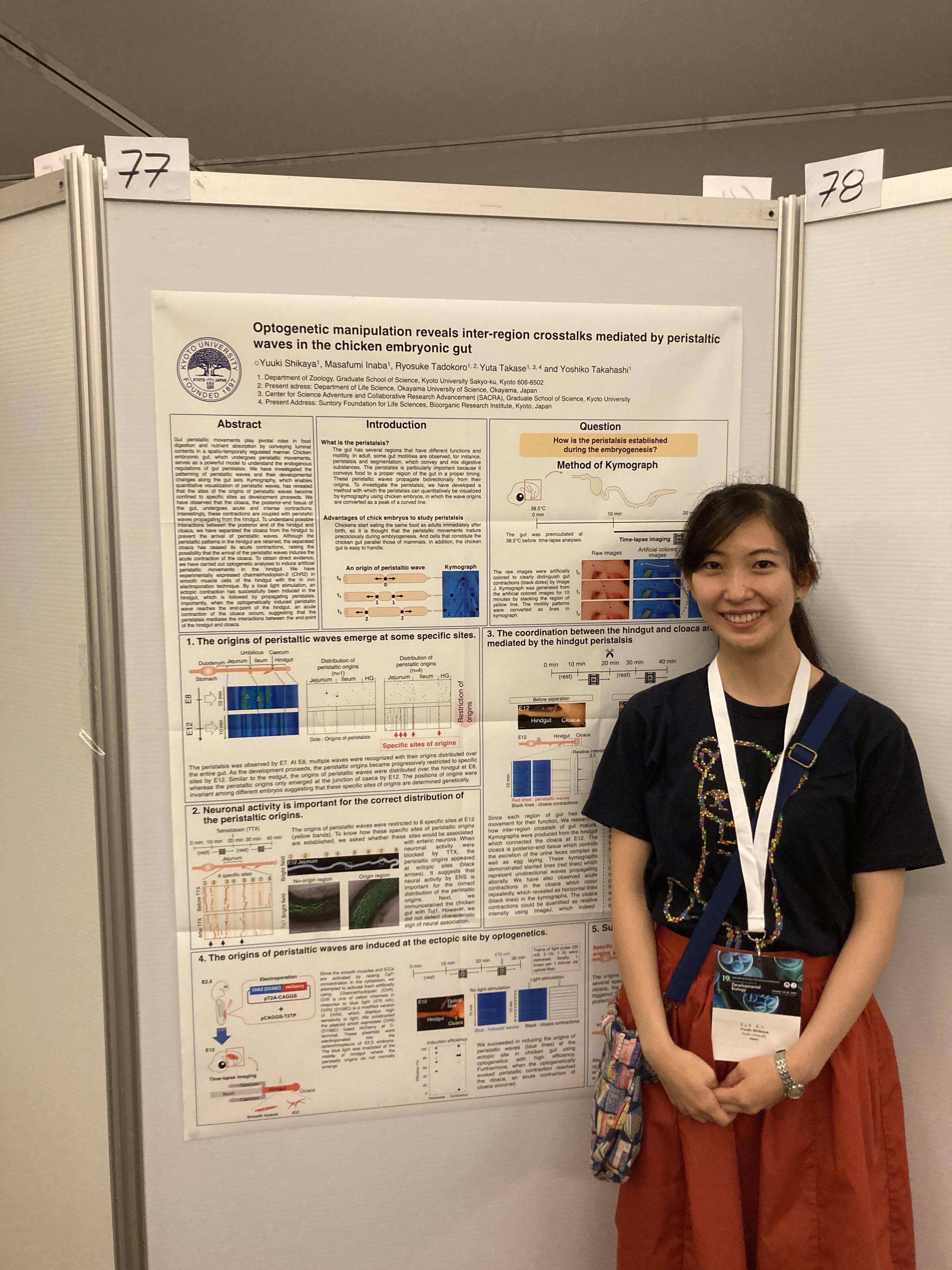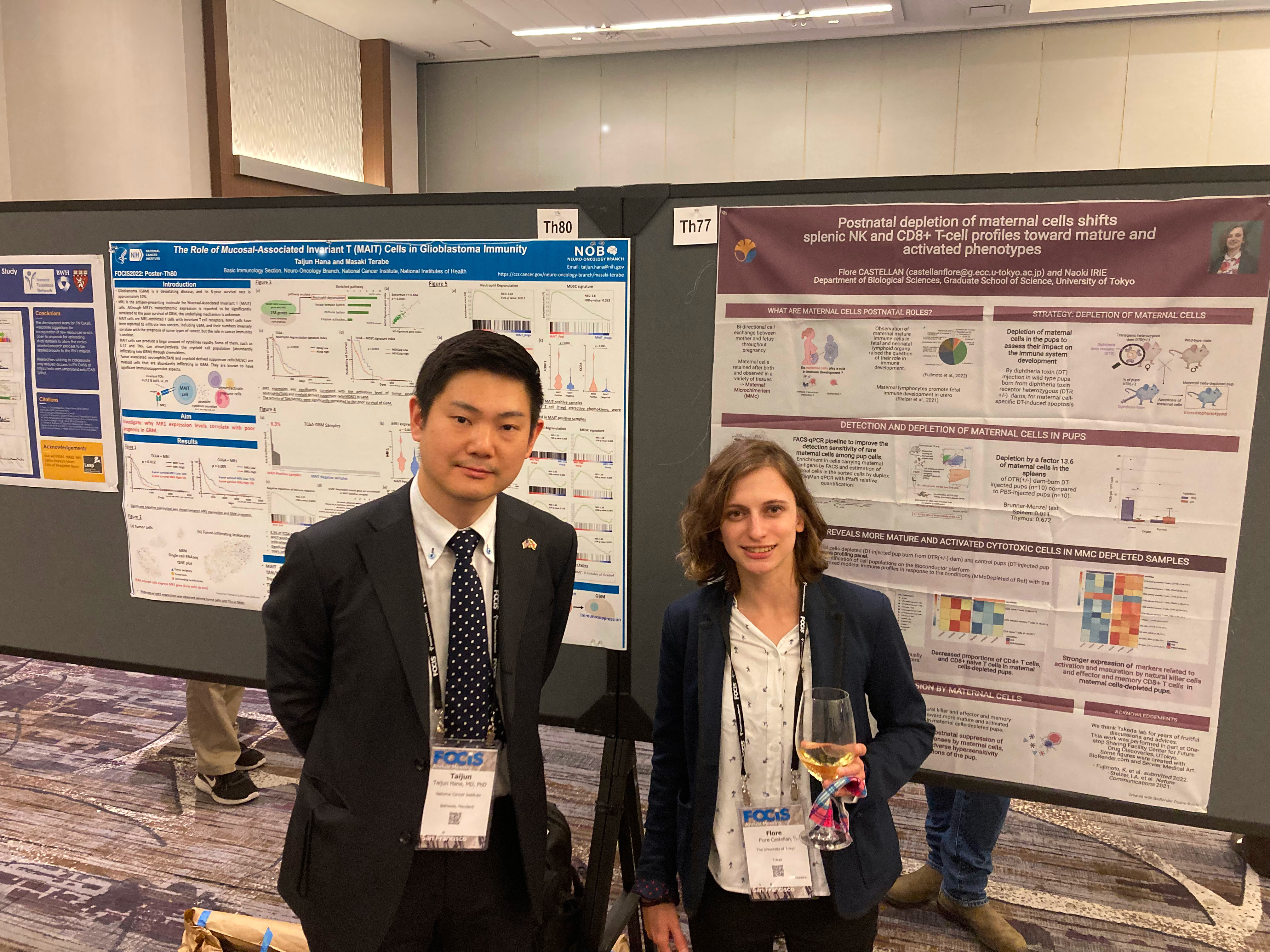2022.12.08
岡田節人基金 ISDB海外派遣報告書 浅倉祥文(理研BDR)
理化学研究所生命機能科学研究センター
浅倉祥文(博士研究員)
浅倉祥文(博士研究員)
日本発生生物学会岡田節人基金若手研究者海外派遣助成をいただき、2022年10月16日から20日にポルトガル南部Algarve地方のSalgadosという町で開催された、19th International Congress of Developmental Biologyに参加しました。
コロナウイルスCOVID-19感染症の世界的流行の影響が残る中での海外学会参加でしたので、その点についても経験したことを記載いたします。今後海外へ渡航される方の参考になれば幸いです。
【19th International Congress of Developmental Biologyについて】
この会議は4年に一度開催されており本来は2021年に予定されていましたが、COVID-19感染症の影響のため1年延期となり、5年ぶりに開催された会議でした。会期中は午前中と夕方に口頭発表があり、昼食の時間を含めて三時間ほどがポスター発表というスケジュールでした。
口頭発表は半分ほどが招待講演者の有名な先生方による発表で、あとの半分ほどは応募者から選ばれた方による発表でした。私は今回ポスターのみで応募したのですが、一体どのような方が口頭発表に選ばれるのか、次回以降に口頭発表に選ばれるにはどの程度の実績や研究内容が必要なのか、という点にも興味を持っていました。すると選ばれた方は若い方が多かったものの、研究室を主宰する立場にあり有名な学術誌に論文を発表したばかりの先生がほとんどでした。また招待講演者の先生方のお話は数十年の研究の積み重ねの上で新たな知見を議論しており、興味深い発表ばかりでした。こうした研究者になれるよう努力しよう、と思いを新たにしましたが、まだ道は長いようです。
また会期全体を通じて、研究手法としてオルガノイドや数理・物理的な手法を用いた研究が多数発表されていたことが印象的で、新しい技術や新しい着眼点に基づく最先端の研究発表を多数聞くことができました。発表を聞きながら私の頭に浮かんだ疑問は多くが発表の中でデータと共に答えが与えられていたのですが、質疑応答の時間には、言われてみれば「なるほど」と思うような鋭い質問が多くなされ、対する発表者の方の答えもスマートで、短い時間の中で非常に内容の濃い議論が交わされていました。
今回私は「Chromatin dynamics during collinear Hox gene expression」というタイトルでポスター発表を行いました。会期中、およそ400名がポスター発表を行っており、ポスター発表の会場は室温が上がるほどの熱気に包まれていました。そのため聞きたいポスターを探すのも、見つけて近くまで移動するのも一苦労という状態ではあったのですが、幸いにも発表時間の間ずっと、興味を持ってくださった方と議論することができました。ただ最も熱心に話を聞いてくださり様々な質問や提案をくださった方が、異なる発生ステージでほぼ同じ実験を予定してグラントをとったばかりだと去り際に教えてくださり、実は競争相手を見つけたので進捗状況に探りを入れる目的もあったのでは、と焦る場面もありました。しかしこうした議論の中で、研究成果の論文化までに必要な要素やさらなる発展の可能性が具体的に見えてきた点が大きな収穫でした。
【COVID-19感染症流行下での海外渡航について】
2019年の年末ごろから本来の開催予定だった2021年にかけてはCOVID-19の影響から多くの学会が中止や延期となり、開催されてもオンライン会議が主という時期でした。しかし今回はポルトガルの会場で現地開催の会議に参加することができました。
会議の開催された2022年の10月は、国内ではまだマスクを外して外出する人はほぼおらず、感染対策が国レベルで徹底されていましたが、経済活動とのバランスが議論されはじめた時期でした。例えば9月までは、日本入国の飛行機への搭乗前72時間以内のPCR検査で陰性を証明する必要があったのですが、この検査はワクチン接種回数が3回に満たない者のみと変更され、ワクチン接種が3回以上の者は入国前の検査が不要となりました。そのためニュースでは来日する観光客も増え始めていると言っていましたが、日本国内の空港では人はまばら、という状況でした。
対してポルトガルや途中の飛行機の乗り継ぎで立ち寄った国では、空港は真っ直ぐ歩けないほどの人で混雑しており、飛行機内や電車中でもマスクをしている人は0.1%もいませんでした。その割には咳やくしゃみをしている人が多く居ましたが。また、利用した航空会社からは「日本出国前72時間以内のCOVID-19陰性証明を携行」するよう案内があったものの、携行していた陰性証明の提示を現地で求められることはなく、流行は終わったものとして扱われている印象でした。
こういった状況下での学会参加でしたので、学会会場で会った日本人の方は皆さん3回のワクチン接種を済ませたと仰っていました。しかし私は2回目接種日から開けるべき日数のため3回目接種が間に合わず、帰国前の72時間以内の検査で陰性証明をする必要がありました。そのため万一のCOVID-19感染もカバーする海外旅行保険を契約し、さらにほとんどの航空会社で機内持ち込みが許可されているウェットティッシュ型の消毒用アルコールや大量のマスクを日本から持参し、感染しないよう注意しながらの学会参加となりました。会場では食事中にも議論が交わされている中、感染の可能性が気になって食事中は話をするのを躊躇ってしまい、今回の学会参加で心残りな点となってしまいました。
また帰国用の検査のため、日本の指定の書式で結果を発行してくれる検査場を探したところ、ヨーロッパでは既に検査が必要な場面がほぼ無いためか、学会会場から50km離れた街まで行かないと検査が受けられませんでした。今回私は幸いにも、なんとか辿り着いた検査場で陰性証明が得られたのですが、今後の海外ではCOVID-19の検査が可能な場所を探すのも難しくなると思いますので、その点も下調べが重要だと思います。
今後は日本でもCOVID-19の影響は緩和していくと期待したいですが、それまではワクチンを何度も打ち、マスクや手洗い、アルコール消毒などの感染対策を続けるのが得策なのだろうと思います。
【謝辞】
最後に、今回の学会参加を後押ししてくださった所属研究室の森下先生と共同研究者の鈴木先生、そして日本発生生物学会関係者の皆様と故岡田節人先生に深く感謝いたします。貴重な経験を積ませて下さり、ありがとうございました。
コロナウイルスCOVID-19感染症の世界的流行の影響が残る中での海外学会参加でしたので、その点についても経験したことを記載いたします。今後海外へ渡航される方の参考になれば幸いです。
【19th International Congress of Developmental Biologyについて】
この会議は4年に一度開催されており本来は2021年に予定されていましたが、COVID-19感染症の影響のため1年延期となり、5年ぶりに開催された会議でした。会期中は午前中と夕方に口頭発表があり、昼食の時間を含めて三時間ほどがポスター発表というスケジュールでした。
口頭発表は半分ほどが招待講演者の有名な先生方による発表で、あとの半分ほどは応募者から選ばれた方による発表でした。私は今回ポスターのみで応募したのですが、一体どのような方が口頭発表に選ばれるのか、次回以降に口頭発表に選ばれるにはどの程度の実績や研究内容が必要なのか、という点にも興味を持っていました。すると選ばれた方は若い方が多かったものの、研究室を主宰する立場にあり有名な学術誌に論文を発表したばかりの先生がほとんどでした。また招待講演者の先生方のお話は数十年の研究の積み重ねの上で新たな知見を議論しており、興味深い発表ばかりでした。こうした研究者になれるよう努力しよう、と思いを新たにしましたが、まだ道は長いようです。
また会期全体を通じて、研究手法としてオルガノイドや数理・物理的な手法を用いた研究が多数発表されていたことが印象的で、新しい技術や新しい着眼点に基づく最先端の研究発表を多数聞くことができました。発表を聞きながら私の頭に浮かんだ疑問は多くが発表の中でデータと共に答えが与えられていたのですが、質疑応答の時間には、言われてみれば「なるほど」と思うような鋭い質問が多くなされ、対する発表者の方の答えもスマートで、短い時間の中で非常に内容の濃い議論が交わされていました。
今回私は「Chromatin dynamics during collinear Hox gene expression」というタイトルでポスター発表を行いました。会期中、およそ400名がポスター発表を行っており、ポスター発表の会場は室温が上がるほどの熱気に包まれていました。そのため聞きたいポスターを探すのも、見つけて近くまで移動するのも一苦労という状態ではあったのですが、幸いにも発表時間の間ずっと、興味を持ってくださった方と議論することができました。ただ最も熱心に話を聞いてくださり様々な質問や提案をくださった方が、異なる発生ステージでほぼ同じ実験を予定してグラントをとったばかりだと去り際に教えてくださり、実は競争相手を見つけたので進捗状況に探りを入れる目的もあったのでは、と焦る場面もありました。しかしこうした議論の中で、研究成果の論文化までに必要な要素やさらなる発展の可能性が具体的に見えてきた点が大きな収穫でした。
【COVID-19感染症流行下での海外渡航について】
2019年の年末ごろから本来の開催予定だった2021年にかけてはCOVID-19の影響から多くの学会が中止や延期となり、開催されてもオンライン会議が主という時期でした。しかし今回はポルトガルの会場で現地開催の会議に参加することができました。
会議の開催された2022年の10月は、国内ではまだマスクを外して外出する人はほぼおらず、感染対策が国レベルで徹底されていましたが、経済活動とのバランスが議論されはじめた時期でした。例えば9月までは、日本入国の飛行機への搭乗前72時間以内のPCR検査で陰性を証明する必要があったのですが、この検査はワクチン接種回数が3回に満たない者のみと変更され、ワクチン接種が3回以上の者は入国前の検査が不要となりました。そのためニュースでは来日する観光客も増え始めていると言っていましたが、日本国内の空港では人はまばら、という状況でした。
対してポルトガルや途中の飛行機の乗り継ぎで立ち寄った国では、空港は真っ直ぐ歩けないほどの人で混雑しており、飛行機内や電車中でもマスクをしている人は0.1%もいませんでした。その割には咳やくしゃみをしている人が多く居ましたが。また、利用した航空会社からは「日本出国前72時間以内のCOVID-19陰性証明を携行」するよう案内があったものの、携行していた陰性証明の提示を現地で求められることはなく、流行は終わったものとして扱われている印象でした。
こういった状況下での学会参加でしたので、学会会場で会った日本人の方は皆さん3回のワクチン接種を済ませたと仰っていました。しかし私は2回目接種日から開けるべき日数のため3回目接種が間に合わず、帰国前の72時間以内の検査で陰性証明をする必要がありました。そのため万一のCOVID-19感染もカバーする海外旅行保険を契約し、さらにほとんどの航空会社で機内持ち込みが許可されているウェットティッシュ型の消毒用アルコールや大量のマスクを日本から持参し、感染しないよう注意しながらの学会参加となりました。会場では食事中にも議論が交わされている中、感染の可能性が気になって食事中は話をするのを躊躇ってしまい、今回の学会参加で心残りな点となってしまいました。
また帰国用の検査のため、日本の指定の書式で結果を発行してくれる検査場を探したところ、ヨーロッパでは既に検査が必要な場面がほぼ無いためか、学会会場から50km離れた街まで行かないと検査が受けられませんでした。今回私は幸いにも、なんとか辿り着いた検査場で陰性証明が得られたのですが、今後の海外ではCOVID-19の検査が可能な場所を探すのも難しくなると思いますので、その点も下調べが重要だと思います。
今後は日本でもCOVID-19の影響は緩和していくと期待したいですが、それまではワクチンを何度も打ち、マスクや手洗い、アルコール消毒などの感染対策を続けるのが得策なのだろうと思います。
【謝辞】
最後に、今回の学会参加を後押ししてくださった所属研究室の森下先生と共同研究者の鈴木先生、そして日本発生生物学会関係者の皆様と故岡田節人先生に深く感謝いたします。貴重な経験を積ませて下さり、ありがとうございました。